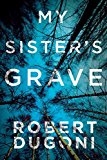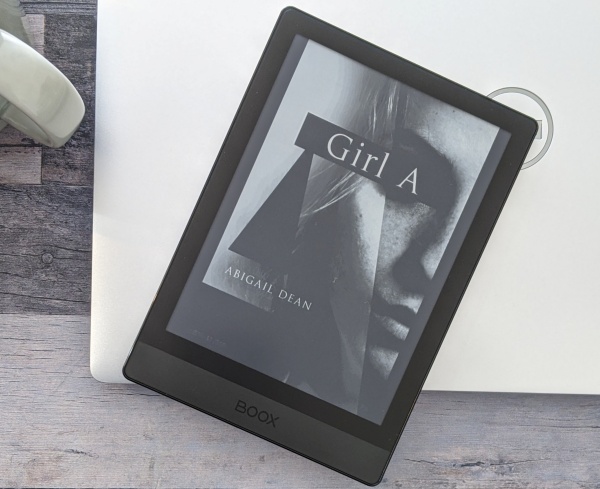今年1月に出たアビゲイル・ディーンのデビュー小説、Girl Aを読み終えました。
エージェントにより出版権がオークションにかけられ、6桁の金額で競り落とされたという話題作です。
著者は2作目の執筆にとりかかりつつ、今もGoogleで弁護士として働いているそう。
あらすじ
ベースとなるのは、実の両親による、7人の子への監禁虐待事件です。
物語のはじまりの部分で、きょうだいのうちのひとりが逃げ出し通報した結果、子供たちは解放され、父親は自殺し、母親は終身刑となっていることがわかります。
脱走し、彼女ときょうだいたちを救った「少女A」であるLexは、現在はニューヨークで弁護士をしています。
母親は刑務所内で亡くなりましたが、死の間際に遺言執行人としてLexを指名していました。彼らにのこされた遺産の処理のため、Lexがきょうだいたちに連絡を取り、それぞれの意思を確認しなければならなくなったのがことのはじまりです。
全体的に暗いです。
彼らの「それから」
著者自身がインタビューで語っているように、どうやって監禁生活から脱するか、というところではなく、苛酷な経験をしたあときょうだいのひとりひとりがそれをどのように克服していくか、ということがメインになっています。
同じ「実の親から虐待されている子供」という立場であっても、きょうだいの数が多ければ多い分、置かれている状況にはグラデーションがあり、そのつらさ、生きる支えになる感情はそれぞれ異なっています。解放されてからきょうだいたちはそれぞれ別の家庭に養子としてもらわれていきましたが、いい育て親にめぐまれた子もいれば、そうでない子もいる。自分の過去を隠して生きている子もいれば、そうでない子もいる。
Lexがひとりひとりを訪ねていく中で、きょうだいたちのたどってきた人生や現在の状況、そして心に秘めていたものが明らかになっていきます。
こどもへの虐待の描写が全体にわたって続くので、このタイプの話が苦手な人にはおすすめできない作品です。
ターピン夫妻の事件
著者は実在した複数の事件からインスピレーションを受けたとインタビューでも語っています。
特に、この作品とも多くの共通点がある、13人の子供を監禁していた2018年のターピン夫妻の事件については、この作品を読んだ後、ニュース記事を読みあさってしまいました。この作品を読み終えたらぜひこのニュースチェックしてみてほしいです。事実は小説よりおそろしい。
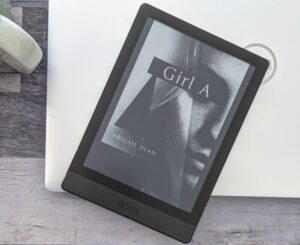
段落ごとに時間軸が変わります。それもしょっちゅう。
昔語りだと思って読んでいたら、いきなり現在に戻っている。
現在の話をしていると思ったら、思い出の中に入ってしまっている。
最初はとてもとまどいましたが、だんだん慣れました。
ちょっと込み入ったこの構成、私は嫌いではありませんでしたが、それが苦手でDNFしたというレビューも見かけました。
あれ?と違和感を抱いたのち、少し戻って再読することで、それまで見えていたものが別のものにすり変わる、それを繰り返しながら少しずつ進み、形づくられていく物語だと思います。