Mohsin Hamidの最新作、The Last White Manを読み終えました。
モーシン・ハミッド
パキスタン・ラホールの出身。父親が大学教授だったことで子供時代の一時期をアメリカで過ごす。パキスタンに戻ったのち、ふたたびアメリカ(プリンストン大学・ハーヴァード大学ロースクール)で学び、卒業後、マッキンゼー・アンド・カンパニーで働く。プリンストン大学ではジョイス・キャロル・オーツやトニ・モリスンに師事。
2001年からはロンドンに拠点を移し、英国とパキスタン、2つの国籍を持っている。ラホールとロンドン、ニューヨークを行き来しながら著作活動を続けている。
2008年のThe Reluctant Fundamentalistおよび2017年のExit West(『西への出口』)はブッカー賞ショートリストにノミネートされたほか、多くの文学賞の受賞作・候補作となった。
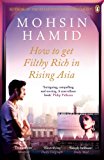
カフカの『変身』めいた冒頭
ある朝青年Andersが目覚めると、自分の肌が白から褐色に変わっていることに気づきます。
作品の冒頭はまさにカフカの『変身』を思い起こさせるもので、読者は不穏な未来を予想しながらページをくることになります。
この変容、実はAndersひとりに起こっているわけではないことが徐々にわかってきます。
白人が大多数を占めるその町のマジョリティが、次第に非白人にとって代わっていき、タイトルの「最後の白人」が誰なのかが明らかにされることになります。
難民をテーマにした前作と同様、非常にメッセージ性の強い、でもそれだけではないおもしろさのある作品となっています。
感想
前作と同様、それほどボリュームはないのですが、読みごたえのある作品です。文章の独特なリズムに慣れるまでに時間もかかりました。小刻みに寄せて返す波のような文章が印象的な作品です。
理由もわからず、集団に変化が起こるというテーマは、ジョゼ・サラマーゴの『白の闇』に通じるものがあるなと感じました。
読み終わってすぐ、タイムリーに著者のインタビュー記事がTwitterに流れてきたので、ラホールからのZoomインタビューの内容を聴きました。
2001年にそれまで住んでいたアメリカを離れロンドンに移ったが、9月11日のアメリカ同時多発テロ事件後、アメリカに帰ると、ひとびとの自分に対する態度がすっかり変わってしまっていた。自分の中身は何も変わっていないのに、まるですっかり外側が変わってしまったように対応された、自分は「白さ」を失ってしまったのだと感じた、とこの作品の背景について語っています。
白人がその白さを失っていくというストーリーの中には、もちろん人種差別の問題も内包しているのですが、それ以上に、物語で描かれている、皆と違ってしまうことへの不安や恐怖、社会のマジョリティであることの安心感とその立場の不確かさ、がとてもリアルに迫ってきました。
前作と同じく、現実に存在する社会問題がテーマでありながら、その問題自体について何らかの解決策が示されるわけではないので、すっきりする読後感ではないのですが、ひとびとの想像力を喚起する物語に圧倒されます。町の人たちの肌の色が変わってしまうという非日常の中で、親子のあいだの愛や葛藤が細やかに描かれるのもよかったです。







