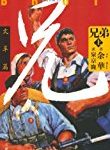留学時、多国籍の生徒で構成されているクラスでは、韓国人の学生がとてもよく発言をしていました。初級レベルでも、知っている単語を駆使して、なんとか自分のいいたいことを表現しようと奮闘している姿に、すごいなあと感心したものです。
それに比べると、日本人学生はおしなべておとなしい。「よくそんなに話すことがあるねえ」と、授業で賑やかな学生に対して言っているのもよく聞きました。中国人学生との相互学習でも、相手ばかりが喋って、結局損をした気になるとぼやくのも日本人です。
その理由がこの本を読んでわかったような気がしました。
日本の「察しあう文化」の是非はさておき、語学学習には「話題を作り出す」「話題を深く掘り下げていく」ことがとても大事だと思います。私はおしゃべりが苦手なので、発話しなければならないときは、できるだけ自分が自信を持って話せるテーマに関連付けるようにしています。映画の話であるとか、読んだ本の話であるとか、引き出しをできるだけ多く持つことも会話には大切ですね。
本の中の「海苔巻きの作り方を知らない人がちゃんと作れるように説明できるか」という問いかけに、思わずうなってしまいました…日本語ですら上手に説明できないかもしれません。
外国語で話す機会がなくても、こんなふうに自分で「私が外国人に説明したいこと」を積極的に探してきて、日本語でいいから作文することも大切かもしれないなと思いました。日本語で話せないことを外国語で話せるわけはありませんから。
そういえば、「自己紹介をたっぷり準備しておきなさい」と薦める英語学習指南書もありましたね…
この本は欧米主要言語を例にとって書かれていますが、提案されているトレーニングは、他の言語にも応用可能です。
たとえば中国語なら「過剰な描写」をこころがけること。しつこいくらいに描写した方が、中国語としては自然になるので、中国語に訳そうとする文章は、あらかじめそのように構成した方がラクかもしれません。
この本、続編もあるようなので、また読んでみようと思います。
書店でざっと斜め読み。「メンタル筋力」が弱い私としては、参考にすべきことがたくさん書いてありました。

起きていることはすべて正しい―運を戦略的につかむ勝間式4つの技術
勝間 和代
結局、現在の自分は過去の自分が選択してきた物事の結果でつくられているんですね。
結婚前の職場では中国語を使った仕事をメインでやってましたが、一時期それと並行して、中国語とは全く関係のない新規立ち上げのプロジェクトを任されました。
わからないことだらけで毎日が勉強、「これは私のしたい仕事じゃないのに」「関係ない勉強ばかりしなければならない」と心の中でちょっと思ったりしていましたが、なんとか踏ん張って立ち上げにこぎつけました。時代の波に乗り切れず、そのプロジェクト自体の結果はあまりかんばしくなかったのですが、そのときに学んだことのお陰で、2人の子供の出産後、今の仕事に就くことができました。
出産前に派遣で行っていた職場も、一般事務だと聞いていたのに実際には資格が一つ取れるほどの専門知識を詰め込んでおかなければできない仕事でした。その知識自体が今後役に立つことがなくても、そこでなんとか前向きに対応したことが、私の経験値になっているかも、とこの本を読んで思いました。(でも本当に、できの悪いスタッフで、毎日毎日怒られて呆れられてたんですけど…)
いいことも悪いこともあって、人生は気の持ちようだな、ということをしみじみ感じ始めています。成功を目指すカツマーのみなさんとは違うかもしれませんが、この本からはそういう「人生気の持ちよう、妬まず、愚痴らず、前向きに、まずは自分をハッピーに!」というメッセージをもらいました♪