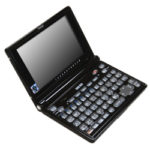今朝の「まいにち中国語」の小野先生、ちょっと調子を出してこられましたね♪
「井戸から女の幽霊が出てきた」なんて例文、普通ちょっとありませんよ。許硯輝さんの例文の読み方も…笑える~。
それにしても今週の存現文、目からウロコがぽろぽろ落ちました。
「下雨了」「雨停了」の語順の違いの説明、今まではなぜ語順が違うのか深く考えず、漠然と使っていたのですが、なるほど~と納得しました。
「まいにちハングル」も、今日のスキットは不思議とすんなり理解できました。小説に関する話題だからでしょうね。興味があるとないとでこれだけリスニング力が違うなんて…。
中国語もハングルもラジオ講座を聞いていて思ったのですが、「きいてわかる」になるまでにもかなりの努力が必要ですが、「きいてわかる」から「自在に使える」ようになるにはまたさらに努力を重ねなければならないのですね。アプローチも変えなければならないし。
ハングルの講座は、復習して単語を覚えれば、なんとか「きいてわかる」状態にまで持っていけます。ですが、それだけでスキットの内容を自由に使えるかというと、まだ全然だめ。
中国語の講座は、「中級」ではありますが、このレベルを使いこなせないと会話らしい会話はできないだろう、という内容ですね。「きいてわかる」だけではだめで、「自在に使える」必要がある内容です。おそらく、今回のハングル講座も同じことがいえるでしょう。
語学学習において、習得した内容は常に「自在に使える」「きいてわかるけど自分の口からは出てこない」のどちらかに分類されるように思います。今の私は、「きいてわかる」レベルの貯金は増えているので、2つのレベルの差を埋めるべく、「きいてわかる」内容をその上の「自在に使える」レベルに持っていく学習法を模索する必要があります。
まだまだ試行錯誤の途中ですが、やはり、ネイティブスピードの音声教材を使って、意味の把握、覚えてしまうまでシャドウイングなどの音読を繰り返す、という学習がいいのかなと思います。音読の際にも、レシテーション、というのかしら?発音だけでなくリズムやピッチにも注意して、感情を込めて読むように気をつけたりとか、いろいろ悩み中です。
ハングル学習の方は、キクタンだけでは覚えられないということを実感。1つの語に3つずつついている例文を使って、書いたり読んだり、五感をフル活用して覚えていくしかないですね。音だけ、しかも単語だけの羅列を聞いて「意味を覚えてやる!」といくら力んでもあまり効果がないとわかりました。キクタンのような教材はむしろ、覚えているかを確認するために繰り返し使う方が効果的なのかなーと思います。
井戸から女の幽霊が出てきた
 未分類
未分類