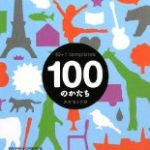近所で中国を教えていらっしゃる方とお話をする機会がありました。
年配の上級学習者が好みそうな小説やエッセイ選びに悩んでおいででした。私自身がそれほどたくさん読んでいるわけではないこと、先生はネイティブで文法説明が苦手そうなこともあり、しっかり解説がついているテキストをおすすめしました。
(これです)

珠玉の中国語エッセイで学ぶ 長文読解の秘訣
子供を産んで自分の時間が圧倒的に少なくなってからも、かろうじて中国語で小説だけは読み続けたお陰か、最近は当代小説ならストーリーを追うのに苦労することはなくなりました。
かなり難しそうな教材(成語の由来とか歴史人物のエピソードとか)を読んでらっしゃる学習者が、簡単なエッセイを薦めても尻込みされてしまうという話を聞くと、私が閲読に苦労しなくなった原因が逆に気になり始めました。
私が最初に書籍を読むのに手をつけたのは、留学して間もない頃で、まだ初級レベルでした。平易な文章で、意味が漢字から大体想像できる経済モノ、しかも米国人著者の翻訳モノでした。専攻が経済だったのでとっつきやすかったということもあります。毎日少しずつ精読しました。
それと並行して、フーダオが三毛の散文を授業に取り入れたので、それも読むようになりました。こちらは授業中に音読もしっかりやりました。散文という性質上、感情と事実、過去と現在と願望が一緒くたに描写されるので、ビジネス本より意味がとりづらかった記憶があります。
わかりづらい文章は、しるしをつけて品詞分けし、理解しました。閲読の教科書なんかは予習でこの作業を必ずやっていたと思います。あとから翻訳・通訳テキストを読んで、自分がやっていたのはスラッシュリーディングやサイトラの類いであることに気づきました。
その頃は、ヒイヒイ言いながらボキャビル対策もしていたので、それほど語彙量があったとも思えません。
それでもなんとか教科書ではない本を読み続けることができたのは、
1.自分がもともと大の本好きだから
2.日本語で大量に読書していた経験が言語を問わず長文読解に役立っている
3.スラッシュリーディングで文の構造の分析をすることに慣れた
ではないかな、という結論に達しました。
1と2は、テクニックとしてすぐに取り入れられるものではないので、興味のある方はぜひ3のスラッシュリーディングを試してみてほしいなと思います。
英語学習系のサイトにスラッシュリーディングの方法はよく紹介されています。
確かchstdさんも、ご自身のしるしをつけながらの読み方を記事で解説して下さってたような気がするのですが、検索で見つけられませんでした。(追記:こちらのページでした。chstdさんありがとうございました!)
必要なのは、語彙量よりもむしろこの構造分析なんじゃないかなと思います。語彙量があっても構造が理解できなければ読めなくて前に進むのがきつい。
そして、長文読解トレーニングは試験の長文問題対策だけでなく、リスニングにだって効果があるのではないかと。ある程度量のあるひとまとまりの文章を、ぱっと見で理解できなければ、耳で聞いただけではなおさら理解できないでしょうから。
もちろんある程度のボキャブラリーがないと、辞書引きだけでへとへとになってしまいますけどね…。韓国語の読書をすらすら読めるようになるにはもうちょっと時間がかかりそうです。
そして「それを言っちゃあ…」なのですが、日本語で理解できない内容は、外国語でも理解できるはずがないんですよね。基本は母語だな、と実感することが最近多くなりました。
語彙力があっても…
 未分類
未分類